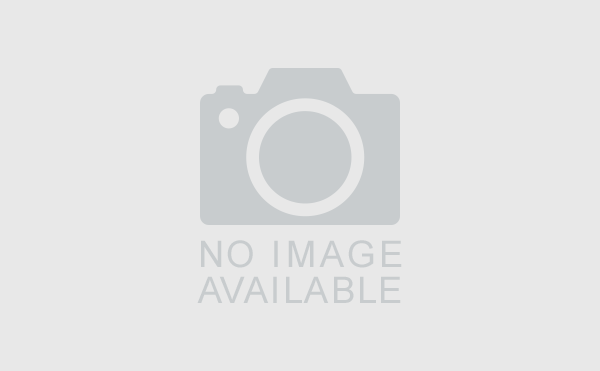基地政策特別委員会 自衛隊基地への視察報告(5/13~15)
5月13日~15日の日程で沖縄県那覇市の陸・海・空の自衛隊基地の視察を行いましたので、報告します。
——————————————————————————————————————————
沖縄県の最大都市であり、31万人が暮らす那覇市の中に陸海空の自衛隊基地が所在している。市内を走る沖縄のモノレール「ゆいレール」赤嶺駅からは基地を望むことができ、那覇基地正門は駅からタクシーで数分の場所に位置する。街中に基地がある暮らしが座間市と同じと感じた。
初日は海上自衛隊へ。まずは格納庫でP-3C哨戒機の説明を受けた。性能がよく信頼性があるとのことで、運用開始から半世紀経った今でも現役であり、潜水艦を探知することが主な任務である。ブリーフィングでは、ジプチ派遣についても説明を受けた。海賊対策のためにジプチに派遣されており、中東の石油等を運ぶタンカーの護衛をし、安全運航を守っている。
群司令との懇談の中では、滑走路の軍民共用について意見交換があった。定時に離陸を目指す民間機と緊急発進もしうる軍用機の両者をうまくミックスさせることが、難しさはあるが、航空管制の腕の見せ所でもあるという。また、「一番戦いたくないのは自衛隊員である」という群司令の言葉が胸に響いた。
次に、航空自衛隊那覇基地に行った。那覇基地には第9航空旅団が配置されており、南西方面の空を守る任務を任されている。那覇空港を軍民共用で使用しており、国交省管制のもと運用されている。2020年には滑走路が2本になった。できるだけ民間に影響のないように配慮されているが、那覇基地はスクランブル発進もあり、2024年は全国で年間704回、そのうちの6割である411回は那覇基地で行われたという。南西諸島の緊迫感の表れと感じる。その後実際にF-15戦闘機の操縦席なども見せていただいた。
ブリーティング後は航空基地の中で恐らく一番高い場所にある古い砲台まで登った。キャンプ座間も座間丘陵に位置するが、那覇基地も高台にあることを感じた。また座間市のかつては陸軍士官学校であった富士山公園には方位盤があったが、この高台にも「首里」などの方角を示した古い方位盤が残されており、座間キャンプとの共通点を感じた。一方、基地の8~9割は借地であるという説明もあり、陸軍士官学校時代に多くの土地を地主から買い取ったという座間キャンプと比べると膨大な賃借料がかかっているであろうことも推察された。
最後は、陸上自衛隊那覇駐屯地へ。陸上自衛隊第15旅団は、沖縄県内で今も多く残されている不発弾の処理にあたっている。沖縄戦では火薬が20万トン使われたといわれており、そのうち1万トンは不発弾と言われている。1974年に子どもが犠牲となる痛ましい事故が起きたことがきっかけで不発弾処理班が結成された。以来4万件処理してきたが、まだ1900トンの不発弾が残っており、すべて処理をするのにあと70年かかると言われている。
不発弾の処理時にこれまで事故が起こったことがないという説明を受け安堵したが、視察後、米軍嘉手納弾薬庫にて不発弾の爆発により作業にあたっていた隊員4名が負傷したという報道にふれた。陸海空に共通することだが、自衛隊員の皆さんが命をかけて任務を担ってくれていることを実感するとともに、戦後80年経っても今なお残る負の遺産に沖縄の人々が苦しめられていることを痛感した。戦争を起こさせないための不断の努力が、世界情勢の緊張が高まる今、一層必要とされていると感じた。